自動車保険 修理の5原則
投稿日 : 2025/10/16
最終更新日時 : 2025/10/16
投稿者 : 事故研いしかわ
カテゴリー : 注目記事
今回の記事は少し難しいので
ゆっくりとひとつひとつを
かみくだいて書きました。
何度も読んで理解ください。
自動車事故保険修理にあたり
被害者立証責任の役目にあたる
保険会社へ提出する
損害算定見積書 の根拠である
「復元修理」の5原則は以下です。
① 性能の回復
② 安全性の確保
③ 耐久性の確保
④ 美観の回復
⑤ 経済性の確保
①の性能の回復とは
自動車本来がもつ
走る 曲がる 止まるの機能が
修理により事故直前の状態にもどす
ということが大前提です。
性能は機械や製品の性質 能力です。
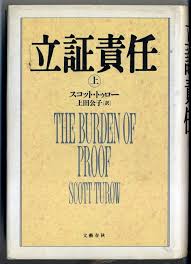
②の安全性の確保とは
ある物事の安全の度合いのことで
(リスクが許容可能な水準に
抑えられている状態)
安全とは 言い換えれば
事故・災害・犯罪などの危害に対して
個人や一般社会が許容できる限度に
抑えられている状態のことをいう
であれば自動車事故で失った機能を含め
安全性が十分に担保される修理である
ということが容易に理解できます。
③の耐久性の確保ですが
耐久とは
長期にわたって使用されることであり
確保とは 確実に手に入れるという意味
すなわち
修理において壊れないものを
長期にわたり 確実に手に入れなさい
と解釈できます。
そして④の美観の回復は
読んで字のごとく
美しく見えなければダメとなります。
自動車事故の修理には美しさを
元にもどすことが要求されます。
例えば ドアパネルを交換したとなれば
パネルの立て付け( 隙間や段差 )が
合ってないのでは回復とはいえず
また 取替パネルと
ボデ-の色差が判るならば
見た目の美しさが
元通りでないことになります。
⑤の経済性の確保は
上記4つの原則を十分に満たして
修理の質を保証し そのうえで
価格が合理的であることが考慮されます。
支払う側からすれば事故との因果関係の
範囲はもちろん
過剰すぎる修理を認めるとなると
保険システムが崩壊してしまいます。
記憶に新しい 大手保険会社と
ビックモ-タ-間の 不正請求事件が
衝撃すぎて忘れられませんが・・・・。

原則(げんそく) を調べると
もともとの法則 または
多くの場合に共通に適用される
きまりになります。
これらの原則を守ることで
修理業者は事故被害者に対して
信頼性の高い損害算定
を提供できるようになります。
対する 消費者(被害者)は
事故で損害算定見積書の作成を
お願いするならば
これらの原則が守られているかを
確認することがとても重要です。
「このくらいなら大丈夫だろう」とか
「見えないけど多分大丈夫だろう」など
の見解は保険会社側が経験則として
かなりの割合で主張してきますが
数字的な物証や
他の確証がなければ
その主張に責任はまったくありません。
協定してしまえば あとは関係なし。
賠償金は保険金の本来の請求権者である
被害者が契約に基づき保険金請求する。
そのあとで
修理代金は修理工場と被害者の依頼者が
修理契約において自由契約するのが
消費者の権利を
満たした契約なのです。
つまり損害賠償金と修理費は
違うという事であり
賠償保険金は修理代ではなく
損害額であるという事を
消費者も修理事業者も再認識して
被害者救済に役立ててください。

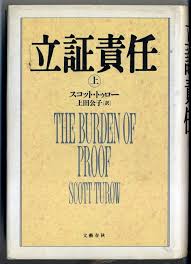

 総合・その他の情報2026.01.01近未来の無人運転タクシ-
総合・その他の情報2026.01.01近未来の無人運転タクシ- 注目記事2025.12.15CANインベ-ダ- とは
注目記事2025.12.15CANインベ-ダ- とは 被害者のためになる情報2025.12.01共同不法行為
被害者のためになる情報2025.12.01共同不法行為 注目記事2025.11.16メ-カ-補給部品 価格高騰
注目記事2025.11.16メ-カ-補給部品 価格高騰
